学習支援で大切にしている想いの中に
「わかる」「できた」をより多く経験する
というものがあります。
自分自身も子育ての真っ只中で
親として子どもに期待すること
というのは本当にたくさんあるなと感じています。
ただその期待が、本人の負担にならないようにするには
時折周りの人や、信頼できる人から「その子のペースでいいんじゃない」と
声をかけてもらわないといけないなと思います。
親御さんの思いを受け止めながら
お子さんと一緒に歩むことができるようにということを大切にしています。
できた!わかった!の経験を積む
事業の紹介でも書きましたが、学校という集団の場において
「うまくいかない」「みんなと比べて自分はできていない」
と感じてしまうことが積み重なってしまうことがよくあります。
これは、能力ベースではなく年齢ベースで集団を作っているから起こる現象でもあります。
もちろん同年齢の集団でもその「違い」を前向きに受け止められる気質の子や、そういった空気を作り出してくれる学校や先生がいればそれは幾分か軽減されます。
子どもたちに必要なことは
「自分に自信を持つこと」です。
それは、できた!わかった!の実感を持って様々なことに挑戦し
それを積み重ねることで育っていきます。
掛け算が苦手、でも地理は得意
だったら地理の勉強をどんどん進めればいいんです。
もしかすると地理の勉強の中に掛け算の知識が必要になる場面が来るかもしれません。
その時には「この地理の問題を解きたいから掛け算を勉強しよう」
という気持ちになれるものです。
知りたいことは自然と身についてくる
興味があるものやことには自然と知識を得ようとするものです。
好きなゲームの話ばっかりしている。
好きなアニメのものすごくマイナーなキャラの情報を知っている。
など、興味を持つという力はとても大きな学びの原動力になります。
割り算が苦手でなんとか練習させたい
漢字がめっきりダメだから毎日課題をさせてます
と苦手な部分を補おうと周りが必死になっても
果たして本当に本人に身についていくのかということはよく考える必要があります。
苦手なことを突きつけて自信をなくしてしまわないように
そうして、苦手なことばかりにチャレンジしてその都度うまくいかないという思いを経験してしまうと「自信」が失われていきます。
苦手なことに取り組むこと自体が悪いわけではなく
その結果自信をなくしていってしまうことのないように配慮が必要です。
苦手な問題に挑戦する際には、ギリギリ超えられるくらいのハードルまで下げてあげる
超えられるように補助をしてあげることが大切です。
逆上がりの練習を思い出してください。
全く逆上がりができないこに
「はいじゃあ1人でやってみて」
と言ってもそうそううまくはいきません。
その子は自信をなくして「やりたくない」と思ってしまうでしょう。
台を使ったり、大人が手で体を支えたりしながら
その子がギリギリ超えられるハードルを設定してあげることが大切です。
この時に重要なポイントは
そもそも逆上がりができる体の強さがあるか
筋力や関節の状態
その子の気持ちの状態
というものを必ず考慮しないといけないということです。
鉛筆でまっすぐ線を引くこと自体が難しい子に
「自分の名前は漢字で書きなさい」と言っても
それは高すぎるハードルです。
今のその子の状態を把握して課題を設定するということがとても重要だなと思っています。
「何を学ぶか」より「どう学ぶか」を大切に
スモールステップでサポートしています。
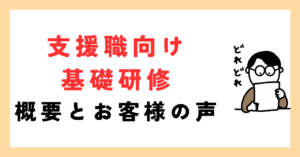
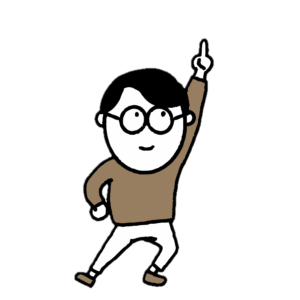
コメント